- Home
- 基本的な勉強方法など
- 試験で出る問題を知りたい人に!
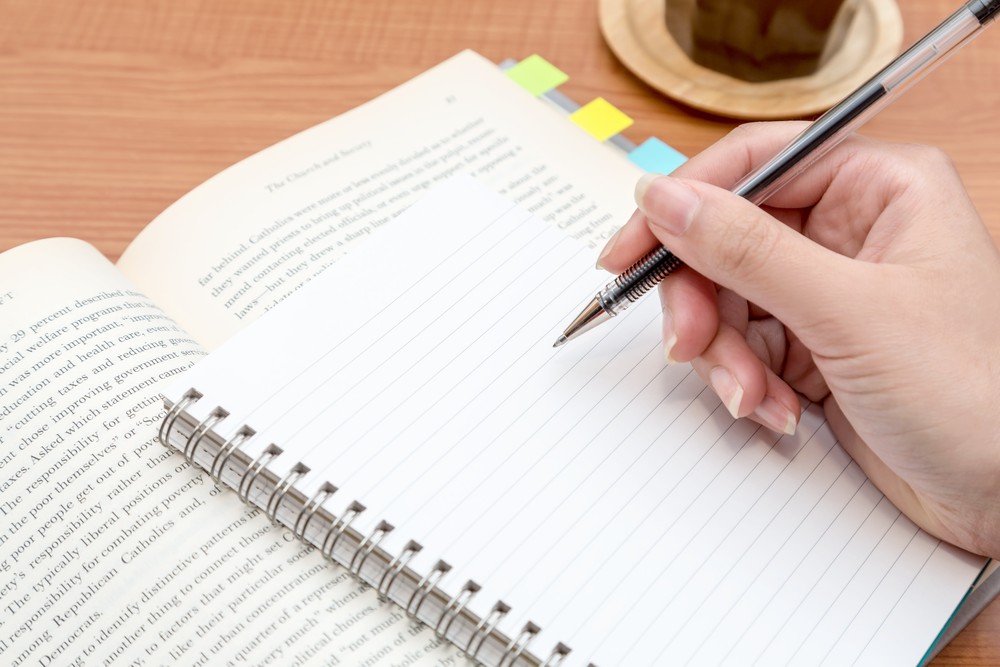
どの受験生も販売士の本試験でどのような問題が出るのかを知りたいと思います。ズバリはわかりませんが、販売士には一定の試験傾向があるので、出題可能性の高低はわかります。では、どうやって販売士の試験傾向を掴むかについて説明します。
販売士は定期的に同じ問題が出ている!だから過去問題で出題傾向を掴む!
販売士の過去問題を何回か解くとわかると思いますが、販売士試験は同じような問題が定期的に出題されています。毎回出題されるポイントもあれば、定期的に出題されるポイントもあります。これらの出題傾向・試験傾向は過去問題を何回か解くことでわかります。
漫然と過去問題を解いていても試験傾向はわからないので、過去問題を解くときは必ず公式テキストや参考書に出題された項目をマークしながら解きましょう。このようにマークすることで公式テキストや参考書の中でマークが重なる項目(出題頻度が高い項目)がわかるはずです。少し面倒ですがマークするときは出題回を併記する方が効果が高いですよ。![]()
販売士2級3級の過去問題は売っていますが、販売士1級の過去問題は売っていません。公式ハンドブックについている1回分のみです。
販売士の過去問題は早めに解く!
「過去問題はいつ解けば良いですか?販売士FAQ」で書いていますが、過去問題は一日でも早い時期に解くべきです。過去問題を本試験前の模擬試験代わりに使っている人がいますが、これは間違った過去問題の利用法です。過去問題は模擬試験ではなく、試験傾向を掴むための大切な教材なので、一日でも早い時期に解くべきです。試験直前に過去問題を解いて点数が悪かったらどうしますか?それから勉強法を変えて合格できたら良いですが、どうでしょうか。
販売士に効率的に合格するためには、まず試験傾向を掴み、それに基づいて勉強をするべきで、この試験傾向を掴むためには過去問題分析が欠かせません。










